関節センターについて
ごあいさつ
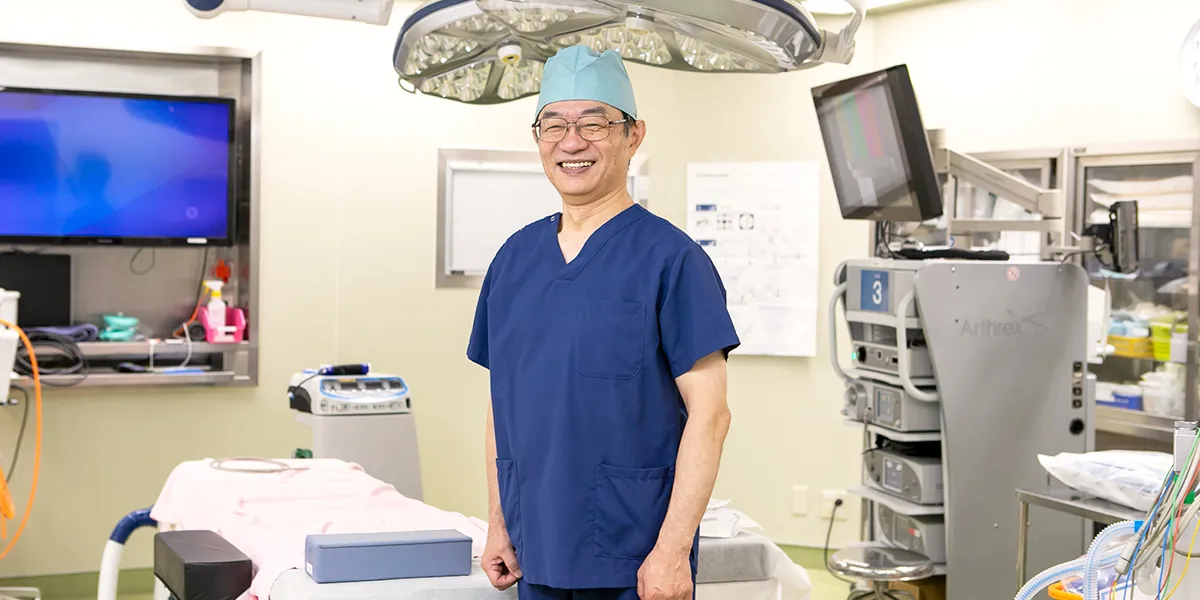
日本は未曾有の高齢化社会になり、膝関節、股関節、肩関節をはじめとする関節の痛みを有する患者さまが急増しています。多くの患者さまは「年齢だから仕方ない」とあきらめていますが多くは治療にて改善が可能です。
また、スポーツなどで膝、足などを痛めた後に、無理してプレイを継続して悪化させる選手も後を絶ちません。われわれはこのような患者さまにより良い医療を提供したいと思い「関節センター」を設立しました。
治療の主体は保存的療法(内服、注射、リハビリなど)と考えています。しかし、保存的療法にも限界があり、効果が得られにくく手術で改善が見込まれる場合には手術が必要と考えます。われわれの「関節センター」は関節の痛みでお困りの患者さまに対して、その人にもっとも適した医療を高い水準で提供します。
当センターの大きな特徴の一つは機動性にあります。大学病院など大きな医療組織では手術が必要と判断しても3-4ヵ月以上お待ちいただくことが多いですが、当センターは病棟・手術室・リハビリの連携を高めることで1-3週間の間には治療を提供できるように努めています。痛みでお困りの患者さまになるべく早く快適な生活を提供したいと思うからです。
もう一つの特徴は、患者さまに手術治療が必要となった場合に、安全で快適な入院生活がおくれるように、医師だけではなくリハビリ、看護師のスタッフ等が一丸になりケアをおこなうチーム医療を徹底していることにあります。関節治療に特化することにより高度な医療を提供することが可能です。
当センターでは急性期病棟(手術後集中的に管理する病棟)に加えて、土日も含めた365日リハビリを行う回復期病棟を有しています。そのために多くの病院が手術後2-3週間で患者さまに退院あるいは転院をお願いせざるを得ないのに対して、当センターでは治療直後の急性期医療から充実したリハビリ医療へスムーズに移行が可能です(*)
より良い医療を速やかに提供する事を目指し、患者さまに「痛みのない生活」をお届けできるようセンタースタッフ全員で努力して行きたいと思います。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。
医師・スタッフ紹介
[医師:センター長]
関矢 仁(せきや ひとし)
| 出身大学 | 秋田大学医学部卒業 |
|---|---|
| 資格・専門医等 | 【略歴】 秋田大学医学部卒業 自治医科大学 大学院卒業(1991年) 米国 MAYO CLINIC 留学(2001年) 自治医科大学整形外科・リハビリテーション 准教授(2006年) 自治医科大学リハビリテーションセンター長(2009年) 新上三川病院 副院長(2015年) 【おもな専門領域】 関節外科(人工関節、スポーツ整形、リウマチ)、手根管症候群の内視鏡治療 |

[医師:副センター長]
高徳 賢三(たかとく けんぞう)
| 出身大学 | 秋田大学医学部卒、自治医科大学大学院卒 |
|---|---|
| 資格・専門医等 | 【 略歴】 秋田大学医学部卒、自治医科大学大学院卒 日本整形外科学会認定専門医 日本整形外科学会認定スポーツ医 日本整形外科学会認定リウマチ医 日本リハビリテーション専門医 【コメント】 関節センターでは、主に膝関節を担当しています。若年者ではスポーツによる膝の半月板損傷や靭帯損傷、高齢者では軟骨の磨り減る変形性膝関節症、関節リウマチの変形などを診療しています。患者さまとよく相談して、痛みなく楽しい生活が出来るように最善の治療を行っていきたいと思います。お気軽に相談してください。 【おもな専門領域】 関節外科(人工関節、スポーツ整形、リウマチ) |

よくある質問
- 人工関節以外の手術は行っていないのですか?
- 人工関節(膝 股関節)以外にも、手・肘・肩・足の関節の診断・治療も行っています。
基本的には、リハビリや薬などの保存的治療を行い、改善しないときには手術を行います。年齢や損傷の程度で関節鏡手術や骨切り術なども行っています。
- 手術にかかる費用はどのくらいですか?
- 一般的に70歳以上の方は1ヶ月の自己負担額は57,600円(別途、食事・部屋代等がかかります)程度となりますが、年齢や所得に応じて負担額は異なります。(令和5年4月現在)
また、70歳未満の方の自己負担額も所得によって異なりますので、詳細は医事課スタッフにお尋ね下さい。
- 日常生活において注意することはありますか?
- 検日常生活において注意することはありますか?
A.膝関節の手術であれば、ランニング、正座などの動作は人工関節に負担がかかってしまうので控えて下さい。ただし、ハイキング、ゴルフなどは可能です。旅行も積極的に出かけて下さい。股関節の手術では、手術方法により制限される行動が異なりますので、リハビリスタッフの指導を守って頂く必要があります。
- 一般病棟と回復期病棟の違いは何ですか?
- 一般病棟(当院では2Fの急性期病棟に当たります)は術前~術後間もない時期に入院する病棟で、回復期病棟は自宅退院へ向けてより集中的にリハビリテーションを行う病棟になります
- 退院後の通院はどうなりますか?
- 退院後は、医師による診察と、リハビリスタッフによる身体機能評価を定期的に行い、手術後1年まで経過を観察します。また、必要に応じて外来リハビリテーションを実施していきます

